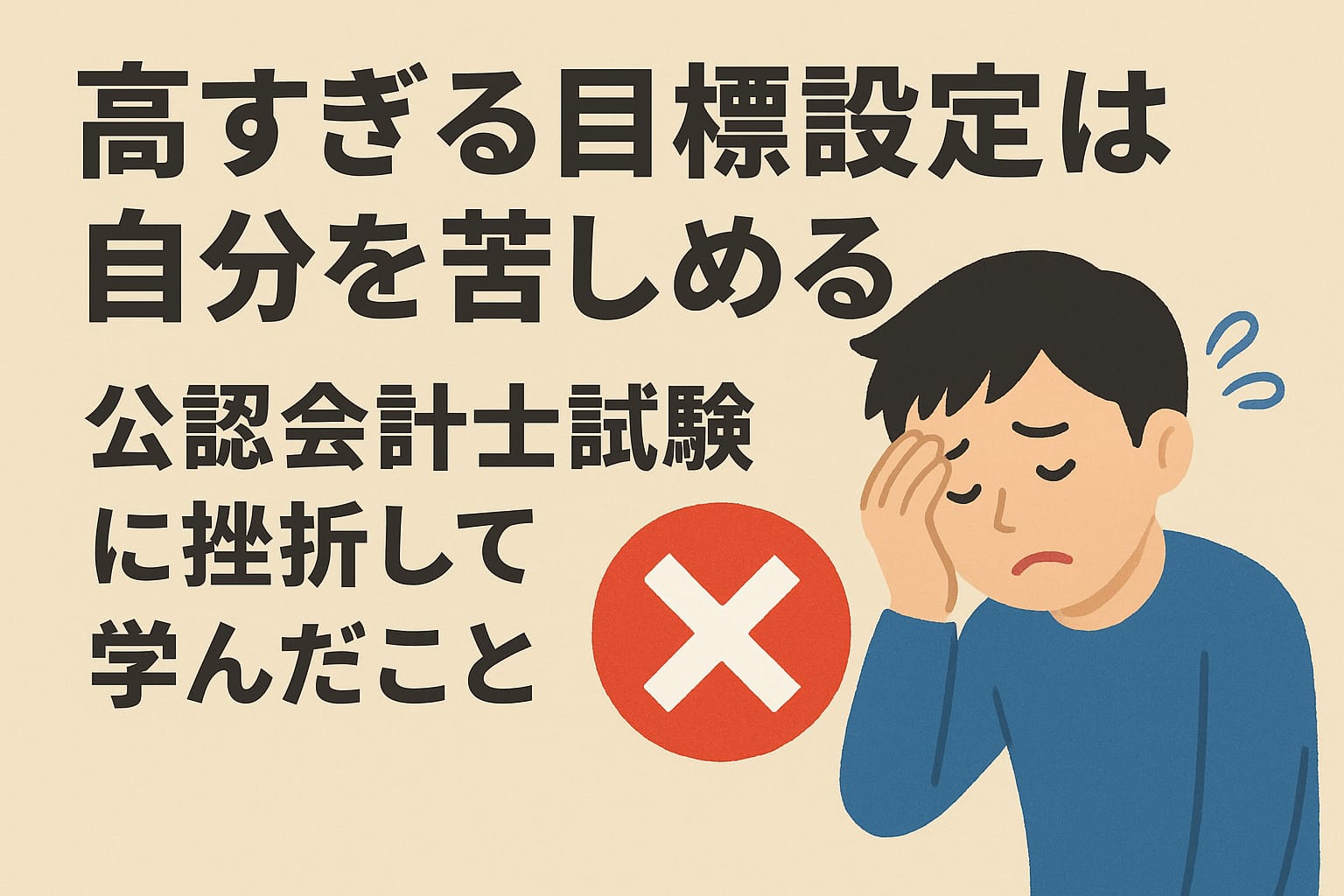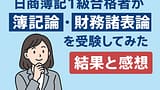はじめに
巷では目標達成のためには、
「夢や理想はでかく持ったほうがいい」
「理想を毎日イメージしていたら叶う」
「努力し続ければ超えられない壁はない」
等言われていますが、これは本当にその人の状況によると思います。
あと少しで夢や目標まで手が届きそうな人は、上記のような名言に救われて、達成できることがあります。
しかし目標とのギャップが大きすぎる人は、こういった考えに囚われて逆に悪循環に陥ることがあります。
この記事では、筆者が公認会計士試験に執着したことで陥った悪循環と、そこから学んだ教訓についてご紹介させていただきます。
公認会計士試験に長年受からなかった時の話
会計士試験を志した動機
会計士試験を志した理由は、大学生という時間がたくさんある時期に、遊びやバイトで埋め尽くして、数年をなんとなく過ごすのはもったいないと感じたからです。
大学生活の数年を遊びやバイトに時間を費やしている間に、優秀な人たちはスポーツや学業で今も努力をして、将来的に大きな活躍をするであろうと考えたときに、「自分も何か1つ挑戦してみよう」と思いました。
そうして大学1年の冬に習い事やバイト、無駄な遊び等をやめて、公認会計士試験の勉強を始めました。
はじめは好調
大学が遠かったので、以下のような生活リズムでした。
朝7時前に出発→電車で勉強→0限(8時15分)から小テスト→空きコマも自習→18時から20時まで夜の小テスト→22時前に帰宅
ほとんどずっと大学にいる生活でした。
途中からは土曜日も大学に通いました。
その結果、はじめて2か月で簿記2級に合格。
成長や充実を感じていましたし、周りからも期待をされていました。
このまま努力を続けていれば、目標を達成できると思っていました。
停滞
しかしその後の会計士試験の勉強で停滞しました。
簿記2級までの勉強方法では太刀打ちできず、いろいろな方法を本やネットで探して試したり、合格者や先生に相談もしましたが、まったく合格できるイメージが付きませんでした。
「講義を見て問題を解け」
「短期で合格すると目標を掲げたんだからあきらめるな」
等先生に言われましたが、参考になりませんでした。
はじめは期待して優しく接してくれていた先生も、段々とあたりがきつくなって近づかなくなりました。
周りはどんどん諦める
そのころには、大きい教室が満杯になるくらい居た会計士受講生の大半は、消えていました。
辞めた人たちに比べて、自分はうまく行かなくても継続して努力しているし、将来良い事があると思っていました。
しかし予備校の厳しいクラスに入って猛勉強したり、色々と試行錯誤して、実力は伸びているものの、1次試験の合格すら見えない状況でした。
一般的な学生は就活をして、内定をもらう時期を超えても状況は変わりませんでした。
人より早く将来を見据えて勉強をしていたのに、いまさら諦めることができず試験を続行しました。
このころはまだ、
「継続は力なり」
「今は苦しくても諦めなければ、必ずできるようになるタイミングが来るはず」
「でかい夢掲げて達成するまで、挑戦し続けるのがかっこいい」
と思っていました。
悪循環
しかし会計士試験に労力と時間を割き続けた結果、大学の授業の単位すらぽろぽろ落として、危うく留年しかけたりもしました。
結局それらのストレスから無気力、将来への不安から不眠症にもなり、ゲームに現実逃避もしました。
最悪の循環です。
また何年もの努力や費用、犠牲によって、今更投げ出せなくなります。
「ここまで勉強をやってきて、新卒も捨てたのだから、それ以上の結果を得なければいけない」
こう考えていました。
コンコルド効果というものですね。
周りからの評価
そして会計士試験や実情をよく知る家族や親しい友人以外からは、「まだなんかよくわからない試験に受からない人」というイメージだったと思います。
公認会計士は一般的には知名度が低く、なんの仕事をするのか、どれくらいの難易度の試験なのかが、わからない人のほうが圧倒的多数だからです。
当人たちに全く悪意はありませんが、
「早く受かれよ」
「まだやってんのw」
「もっと頑張れよ」
などと言われました。
いわれたときは受け流すのですが、あとでシャワーを浴びる時や寝る前に思い出して、死ぬほどはらわたが煮えくり返りました。
「次言われたらどう言い返してやろう」と考えて無駄にイライラしたり、時間が経ってもフラッシュバックして腹が立ったりしました。
「なぜ何年も挑戦してきた自分が、やってもない人から上から目線でアドバイスされなきゃいけないんだ」
「なぜ努力してきたのに、落ち目のように扱われなければいけないんだ」
このように考えていました。
他にも好奇心で「試験どう?」と定期的に聞いてくるタイプもいて、だんだん鬱陶しくなって連絡を無視するようになりました。
余談 弱っている人を見ると、アドバイスをしたがる
これは完全に自分の主観であり仮説なのですが、多くの人はうまく行っていない人や落ち込んでいる人を見ると、「元気づけてあげよう」という気持ちになることが多いです。
その結果、相手の悩んでいることが自分の分野外の事でも、自分なりのアドバイスやユーモアを相手に投げかけます。
なので大半のアドバイスや軽口は、善意だったり、深く考えた発言でないことが多いのですが、ストレスが溜まっていると、それを真に受けてしまいます。
しかも、”弱っている人”に安全圏からアドバイスをかけるという構図が、自然と上から目線になりやすいです。
その結果、言われた側は「何も知らないくせに、偉そうに言うな」と感じてしまいます。
ですので他人から要らぬアドバイスを受けたくない時は、親しい人以外には弱みを見せないほうがいい気がしました。
絶望の中で掴んだある一つの仮説
これまでに、成果を出すために良いとされる事は何でもやりました。
- 目標は大きく持つ
- 結果が出なくても投げ出さない
- 失敗や間違いから学び、改善する
- 合格していく人や優秀な人のノウハウを取り入れる
- 挑戦し続ける
予備校を変えたり、勉強法や生活習慣などを改善して、多くの学びや成長を得ることはできましたが、やはり結果がでないことで人生が停滞しました。
それに対して、
- ある程度挑戦して、うまく行かなかったら方向転換している人
- そこそこの目標を立てて達成する人
こういった人のほうが、自分よりもスムーズに人生を進めている気がしました。
ここで一つ浮かび上がった仮説は、
「自分のレベルに合った挑戦に変更したほうが、結果も出やすいし、長期的に幸福で成長するのでは?」
ということです。
挑戦する目標を変更してみた
実際にこの仮説を検証するために、会計士試験を一旦据え置いて、”日商簿記1級”の試験を半年勉強してみました。
会計士試験は4科目で、簿記1級は計算の2科目しかありません。
さらに会計士試験は短答式試験と論文式試験の2回合格が必要ですが、日商簿記1級は1次試験のみです。
教科が少ない分試験時間も半分以下ですし、これまで会計士のために学習した範囲とほとんど同じなので、負担が圧倒的に軽くなります。
その結果、精神的に余裕が生まれるだけでなく、目標達成が近いことによって行動意欲も増しました。
1級合格までの過程については、こちらの記事で詳しく書いています。
メンタルの改善
簿記1級の勉強によって日々成長を感じ、自信や行動力が増してからは、これまではストレスになるために断っていた友人からの遊びの誘いにも、乗ることが出来ました。
卑屈にならずに堂々と現状のことを話せましたし、多少の悪意のない失礼なことを言われても傷つきにくくなりました。
以前は「失礼なことを言われたら、なんて返そう」とか頭でシュミレーションして、自分のモチベーションやメンタルを必死に守ろうとしていましたが、気づいたらその悪癖が無くなっていました。
会計士試験にラストチャレンジ
その後、最後のチャンスと思って、会計士試験に専念しました。
まったく人と遊ばず、没頭して毎日一日中勉強しました。
しかし結果は不合格でした。
そこで完全に踏ん切りがついて、会計士試験を辞めることにしました。
「今の自分のレベルでは、本気でやっても会計士試験は遠い目標」とすんなりと手放すことができました。
これは上記の仮説や簿記1級の勉強にシフトして得た経験から、
「身の丈にあった目標に臨機応変に変えることが、成長や人生の充実の近道」と考え、失敗や挫折、諦めることが悪いことと捉えなくなったためです。
その後日商簿記1級合格
そして会計士試験の約10日後に行われた、日商簿記1級の試験で合格しました。
3回目のチャレンジでした。
応援してくれていた人にも1つ良い報告ができました。
やっと泥沼の悪循環から抜け出すことができました。
また、上記の経験を活かし税理士試験を志しつつ、余暇に英語の学習やブログも始めました。
以前よりも行動力が圧倒的に増えて、毎日が充実しました。
年末に1年間を振り返ったとき飛躍的な成長を実感し、この仮説が自分にとっては最適なのだと実感しました。
そして自然と他者と比較する癖も激減し、マイペースに生きることができるようになりました。
上記の仮説は、自分にとって人生の指針になりました。
(余談)高難易度試験でも短期で受かる人
会計士試験において、短期間(半年とか1発合格等)で合格できる人は、ものすごい学歴を持った人が多いです。(東大京大一橋、旧帝大等)
スタート時点で母集団の平均レベルよりも学力が秀でているため、目標達成が早いのは自然の摂理です。
経験をもとに効率よく勉強し、短期間で成果を感じられるため、勉強にのめり込むことが出来ます。
それを世の中ではよく地頭とか才能といわれますが、そういった方たちは幼少期のころから努力を重ね、難関校に挑戦し、中学や高校受験等で挫折の経験していたりします。
つまり彼らが短期で難関試験に合格できるのは、過去から経験を積み上げてきて、自分のレベルにあった挑戦をしているからだと勝手ながら推測しています。
このようにスタートラインや能力は人それぞれ違うので、他者と比べずに自分に適した挑戦をすることが大事だと思いました。
人生で多くを得るには、できるところから積み上げる
試験で高得点を取るための大事な考え方として、
「難問は後回しにして、まずは簡単なところから解く」
というものがあります。
試験時間が限られている中、点数を最大化するためには、簡単なところから回答し、難問は時間が余ったら手を付けるのが定石です。
また、簡単そうと思って手を付けたけど中々解けない時は、いったん飛ばすのが大事です。
人生という大枠で見ても、時間は有限です。
昔は「人生は長いから数年くらい失っても大丈夫」と軽く考えていましたが、たった数年の遅れで周りとは大きく差が付き、本来できたかもしれない事が年齢的にできなくなることもあります。
ですので、期限を決めて、自分の能力に見合った又は頑張れば届きそうな目標を達成していくことで、結果的に多くのものを得られると推測します。
当初の想定よりもずっと高い壁だった場合は、一度撤退して自分のできるところやできそうなところから挑戦することで、最大限のパフォーマンスを発揮できるのではないかと思います。
執着を手放すとうまくいきやすい
世の中には、初めに掲げていた目標や夢が叶わず、絶望を感じていたけれど、方向転換した先でそれまでの経験が活きて、成功する人が多いように感じます。
自分も会計士試験に挑戦して足掻いたからこそ、日商簿記1級がちょうどいい目標と感じられるほどに成長しました。
ですがあのまま会計士試験に挑戦し続けて、難易度変更をしなかったら人生は停滞したままだったと思います。
まずは挑戦→うまく行かなかったら執着せずに、自分のできることが活かせる分野に転換するのも、成功するための1つの方法だと思います。
まとめ
大きな夢や目標に挑み続けるということは、ロマンがあって一見かっこよく見えるものです。
しかし高すぎる理想や目標を掲げることで、現実とのギャップに苦しんで、めちゃくちゃ苦労する上に結果も出ず、様々な副作用によって悪循環が起きます。
逆に現状のレベルに合わせた目標設定をすることで、意欲が増し、行動力が増し、目標につき進めます。結果、飛躍的に成長し結果が伴うことで、人生が充実します。
人の数だけ適切な成長のための考え方があると思いますが、自分と似たような方の参考になれば幸いです。
日商簿記1級に合格した後、ステップアップして税理士試験にチャレンジした結果について以下の記事にまとめています。