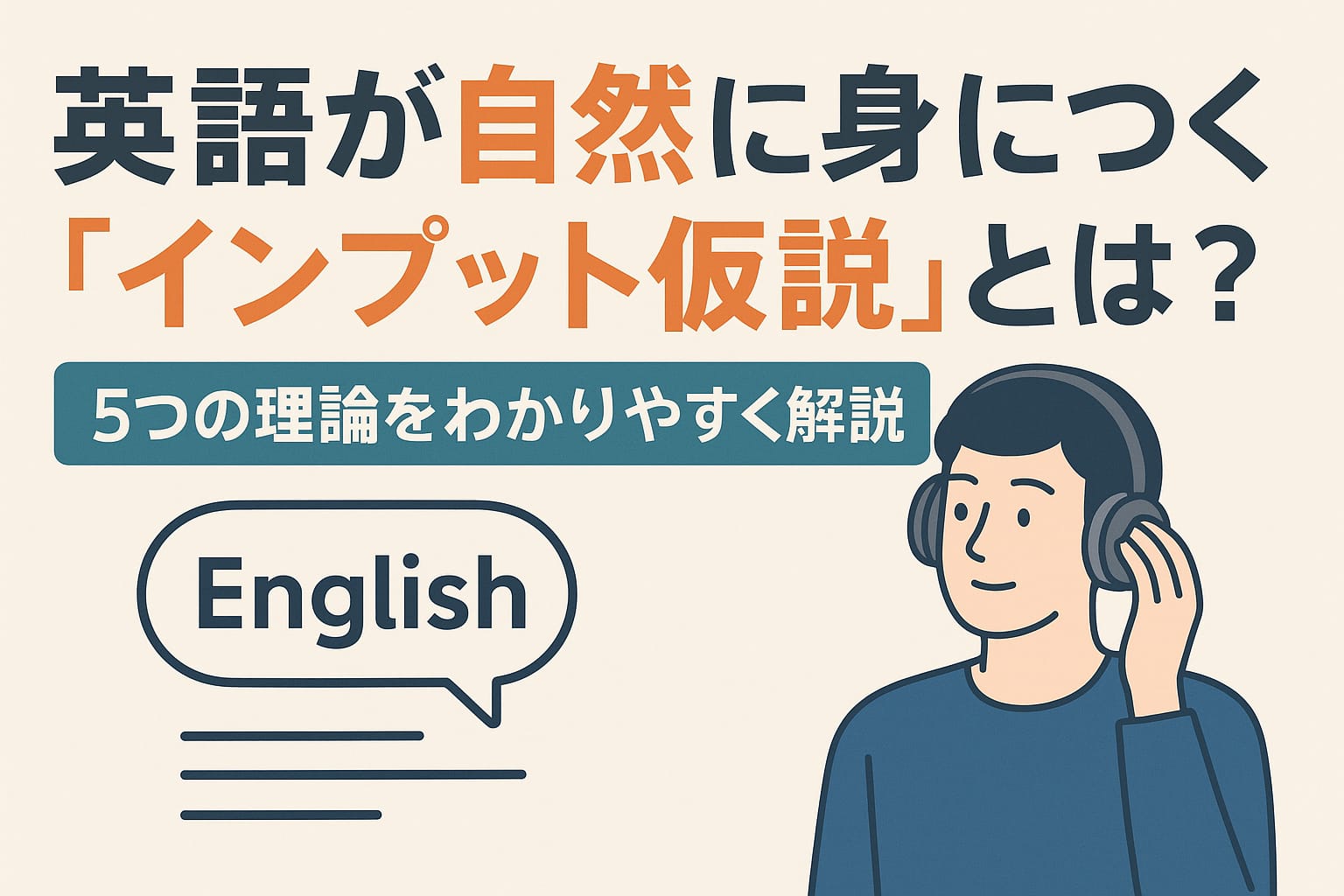インプット仮説(入力仮説)とは?
スティーヴン・クラッシェンという言語学者が1970〜80年代に提唱した理論で、英語を含む「第二言語」をどのように習得するかを説明する考え方のひとつです。
この理論は、以下の5つの仮説で構成されています:
- 入力仮説(一番大事):理解できる言語(=理解可能なインプット)をたくさん受けることが、言語習得の中心になる。
- 習得・学習仮説:言語には「無意識で身につく習得」と「意識的に勉強する学習」があり、この2つは別物である。
- 監視仮説:意識的に学んだ知識は、話すときに「文法チェック」のような形で補助的にしか使えない。
- 自然習得順序仮説:文法や語彙は、決まった順番で自然に身につく傾向がある。
- 情意フィルター仮説:ストレスや不安があると、インプットがうまく吸収できなくなる。
1.入力仮説:一番大事なのは「理解できるインプット」
クラッシェンは「ちょっとだけ背伸びすれば理解できる英語を、たくさん聞いたり読んだりすること」が、言語習得の一番のカギだと主張しました。
この際に、文法を1→2→3…と順番に学ぶ必要はなく、理解可能なインプットがあれば、学習者は自分のペースで自然な順番で習得していくとのことです。
逆に話す練習(アウトプット)は、言語力そのものを伸ばすものではなく、「今ある力を使う」ためのものと考えています。
つまり──
- 文法をガリガリ覚えるだけでは話せるようにならない
- ただ聞き流すだけでも効果は薄い
- 自分が“意味を理解できる英語”を、たくさんインプットすることが重要!
2.習得・学習仮説
スティーヴン・クラッシェンによると、言語を身につけるには大きく分けて、習得と学習の2つのプロセス があります。
① 「習得(acquisition)」とは?=無意識で身につく
- 学習者が 気づかないうちに自然と覚える
- 子どもが母語を覚えるときと同じように、会話や文章との「意味のある接触」を通して進む
- 文法やルールを意識するのではなく、意味の理解に集中している
- たとえ新しい表現を理解できるようになっても、「今習った!」という自覚はあまりない
例:毎日英語のドラマを見ているうちに、自然とフレーズが口から出てくる。
② 「学習(learning)」とは?=意識的に覚える
- 学校の授業のように、文法やルールを 意識的に勉強する
- 新しい知識を「これはこういう文法です」と説明され、間違いを直されながら学ぶ
- フォーカスは「意味」ではなく「形式(ルール・文法)」にある
例:「現在完了形は have+過去分詞」というように、文法ルールを覚える勉強
クラッシェンの主張
- 本当に言語を「使える」ようになるには、習得(無意識のインプット)が重要。
- 学習(意識的な勉強)は、補助的な役割にすぎない。
3.監視仮説(Monitor Hypothesis)とは?
スティーヴン・クラッシェンの「監視仮説」では、
- 「習得された体系」=自然に身についた英語力 が実際に話す力を生み出し、
- 「学習された体系」=文法知識 は、その発話を チェック・修正するだけ の役割だとしています。
つまり──
話すときの「主役」は習得(無意識に身につけた力)であり、学習(文法など)は「添削ツール」のような存在ということです。
監視が働く流れ(イメージ)
- 英語で話す(=習得した力がメインで動く)
- 自分の発話を頭の中でチェック(=文法知識を使う)
- 必要があればその場で修正
例:「He go to school…あ、goじゃなくて goes だ!」
監視をうまく使うための3つの条件
クラッシェンによれば、監視(文法チェック)を使うには3つの条件が必要です。
- 文法を知っていること
修正するにはそもそも知識が必要。でも全ての文法を覚えるのは難しい。 - 正確さに注意できること
意味を伝えながら形式にも注意するのは、かなり負荷が高い。 - 時間があること
会話中に考える余裕が必要。でも実際の会話ではそんな余裕はほとんどない。
監視には限界がある
- 文法を全部覚えている人なんていない。
- 話しながら文法をチェックするとスピードが落ちて、会話がぎこちなくなる。
- そもそも文法は「言語力の一部」でしかない(特に会話では、意味の方が重要)。
クラッシェンの提案
こうした理由から、クラッシェンは――
監視(文法チェック)を使うのは、
- 文章を書くとき
- ゆっくり考えられるとき
など、意思疎通を妨げない場面に限定するべきだとしています。
4.自然習得順序仮説
自然習得順序仮説によると、言語は誰でもほぼ同じ順番で覚えていくとされています。
教えやすさとは関係なく、習得しやすい順番があるという考え方です。
例えば英語では、三人称単数の -s は教えるのは簡単でも、実際に正しく間違えずに使えるようになるのはかなり後になります。
5.情意フィルター仮説
情意フィルター仮説とは、学習者の「感情」が言語習得に影響を与えるという考え方です。
不安・自信のなさ・退屈などのネガティブな感情があると、心に“フィルター”がかかり、言語の理解や吸収が妨げられてしまいます。
逆に、安心して学べる環境や、興味を持てる内容、自信を持てる経験があると、そのフィルターが下がり、言語をよりスムーズに習得できるようになります。
またクラッシェンは、
- 学習者に早く話すことを強要しないこと(沈黙期を尊重する)
- 早い段階で間違いを厳しく直さないこと
が大切だとしています。
批判もある
ただし、この理論はすべての研究者に支持されているわけではありません。
主な批判は以下の2つです:
- 実験で正確に検証しにくい
- 「習得」と「学習」の違いが実証されていない
まとめ
- インプット仮説では、「理解できる英語を大量に受け取ること」が習得の鍵とされている
- 精神的な余裕も大事(リラックスしているほど身につきやすい)
- ただし、この理論にも批判はあるので、万能ではない
出典 インプット仮説 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%83%E3%83%88%E4%BB%AE%E8%AA%AC