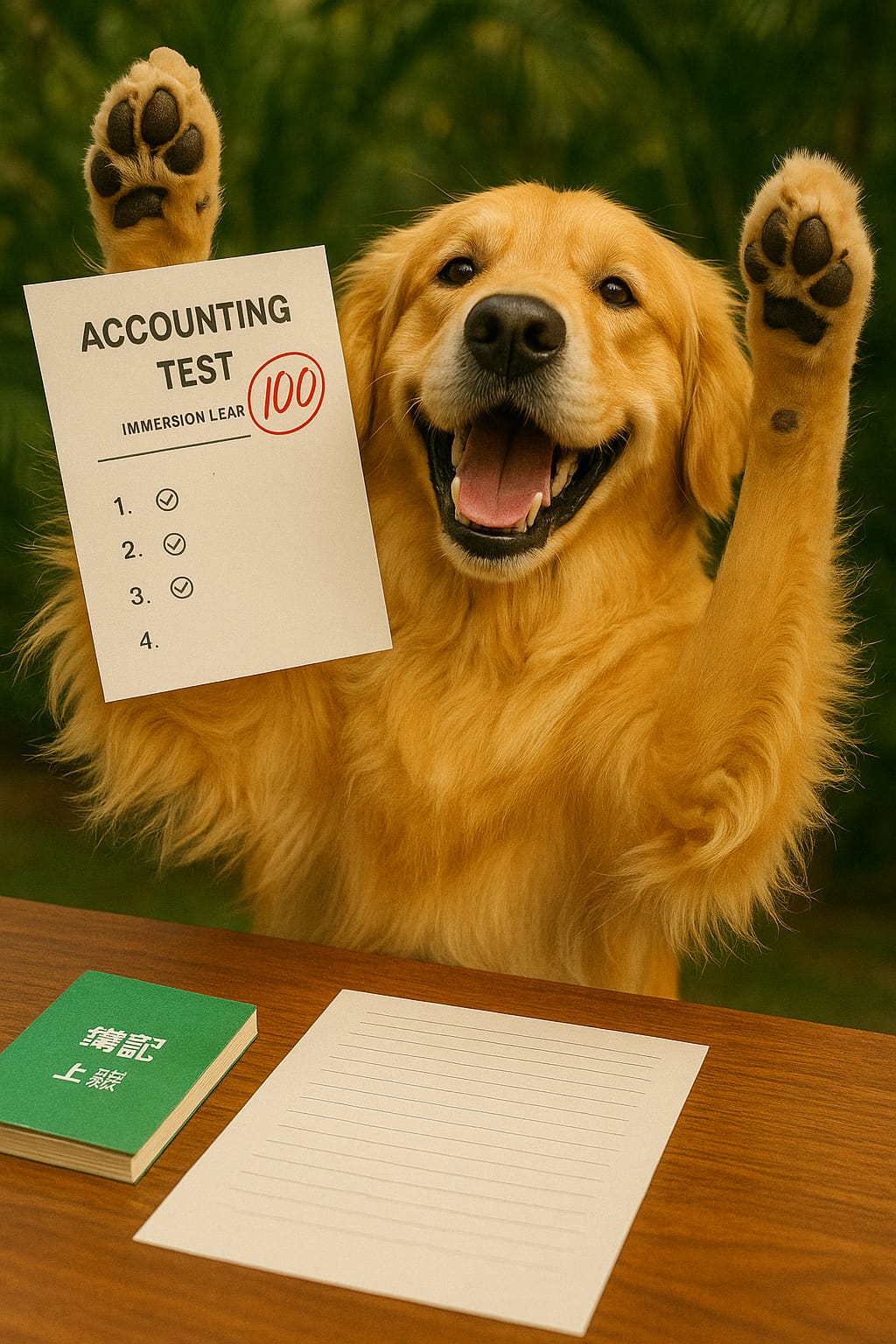はじめに
この記事では、過去問で点数がよくて50点台だった筆者が、簿記1級の本試験2週間前に意識と戦略を変えただけで、点数が急上昇し安定した「解く順番」のコツを実体験を交えて解説します。
日商簿記1級は、知識だけで突破できる試験ではありません。
むしろ、試験中の意識や戦略、問題の捉え方が、点数の安定に大きく影響します。
試験直前の2週間前に点数が安定するようになった試験中の意識改革法を、具体的な行動レベルまで落とし込んで紹介します。
できるところを“常に探す”意識が鍵
試験中、「できない問題にこだわる」のは時間のムダです。
商業簿記では、前から順番に解こうとせず、後ろのほうにある簡単な設問から手をつけるのも立派な戦略です。
- 「今すぐ得点できる場所はどこか?」を常に探す
- 「解けそうで解けない問題」にしがみつかず、1秒でも早く飛ばす
- 難しそうな集計項目(税効果・当期純利益・繰越利益剰余金など)は最初から捨てる
こうすることで、試験全体の構造がクリアに見え始めます。
合格には「傾斜配点」の仕組みを理解することが重要
日商簿記1級は絶対評価ではなく、相対評価によって合否が決まる試験です。
合格率を10%前後にするために、問題ごとの配点が調整される「傾斜配点」が行われています。
この傾斜配点は公式には公表されておらず、試験直後に予備校が出す解答速報の配点と実際の採点結果が大きく異なることも珍しくありません。
そのため、いくつか不正解があっても、「得点しやすい基本問題をしっかり押さえる」ことで、意外にも高得点がつくケースが多くあります。
つまり、「できる問題を優先的に解く」「難問に固執しない」という解法戦略は、日商簿記1級の配点システムに非常にマッチした、合理的な方法です。
傾斜配点の実際の例:ミスが多いのに、満点近くの配点が来た
筆者が合格した第167回の管理会計論は、過去問にない出題形式で面喰いましたが、いったん飛ばして、管理会計の問題を解いた後に、時間の限りできるところを取りに行きました。
結果自己採点では、16点から18点程度の得点でした。
しかし、実際の得点開示ではなんと24点/25点という高得点がついていたのです。
このことから、問題が難しく正答率が低かった問題には、配点がほとんどないことがわかります。
時間と労力を“点につながる場所”に集中させる
簿記1級は部分点の積み上げが非常に重要です。
そのため、「どこに時間をかけるか」は合否を分ける最大の分岐点になります。
時間がかかるうえにミスしやすい場所(例)
- 集計が複雑で、複数の資料にまたがる箇所
- 初見の論点の問題
- 違和感を感じる問題
- 指示が見慣れなかったり、不明確な問題
- 自分の苦手な論点
時間をかけるべき場所
- 単純な仕訳問題や計算問題
- 計算工程が少ない問題
- 指示が明確な問題
- 毎回でてくるテンプレの問題
つまり、難しいところで勝負するのではなく、「取りこぼしをなくす」ことが最優先です。
日商簿記1級では傾斜配点によって配点が操作されます。
基礎的な問題に多くの配点が行くので、こういったところに時間をかけていくことが大事です。
浮いた時間で「見直し・俯瞰・回収」を実行!
戦略的に時間を浮かせることで、次の3ステップが可能になります:
- 俯瞰:全体を見渡し、重要な指示や見落としがないかをチェック
- 見直し:書き漏れ、転記ミス、数字のズレなどを修正
- 回収:飛ばした問題の中から、「今なら取れる」部分を再チェック
このループを回すことで、ケアレスミスは激減し、点数が安定する流れが完成します。
「前から順番に丁寧に」は罠!
順番に前の問題から解いていくと大きく時間をロスしてしまう可能性があります。
前半に時間泥棒な難問が集中しているケースが多いのが日商簿記1級の特徴です。
したがって、最初に全体をざっと見て、「時間をかけずに得点できる問題」に優先的に取り組む姿勢が非常に有効です。
ケアレスミスを防げば、点数は急上昇する
日商簿記1級のように傾斜配点が存在する試験では、ケアレスミスが命取りです。
ケアレスミスによって連鎖的に失点すると、本来なら得点できた10~20点分のロスにつながることも珍しくありません。
ケアレスミス対策をすることで、
- 解きやすい問題を見逃さない
- 時間の余裕ができて、心も安定
- ミスが減って点数が安定
という流れができ、合格が一気に近づきます。
わずか2週間で点数が激変した実体験
筆者自身も、本試験の2週間前にこの考え方に切り替えました。
それまでは時間が足りず、大量に与えられる資料、ケアレスミスに、辟易していました。
しかし「できる問題から解く」「迷ったら即スキップ」「難問は捨てる」といった意識に切り替えたことで、
- 過去問の点数が一気に安定
- 問題がすっきり見えるようになり、取り組みやすくなった
たった2週間でも、“試験中の意識”が変わるだけで得点力がここまで上がるのかと、自分でも驚いたほどです。
まとめ|意識を変えるだけで合格ラインが見える
日商簿記1級は、「すべてを完璧に解く」必要はありません。
大切なのは、傾斜配点の性質を理解し、得点を最大化する意識と戦略です。
2週間で劇的に点数を安定させたいなら、以下を意識することが大切です。
- できる問題を最優先で拾う
- 難しい部分は飛ばしてOK
- 時間を浮かせて、見直し・俯瞰・回収に使う
- 簡単なところでのミスを防ぐ意識を徹底する
たったこれだけで、本番で実力を出し切れる確率が一気に上がります。