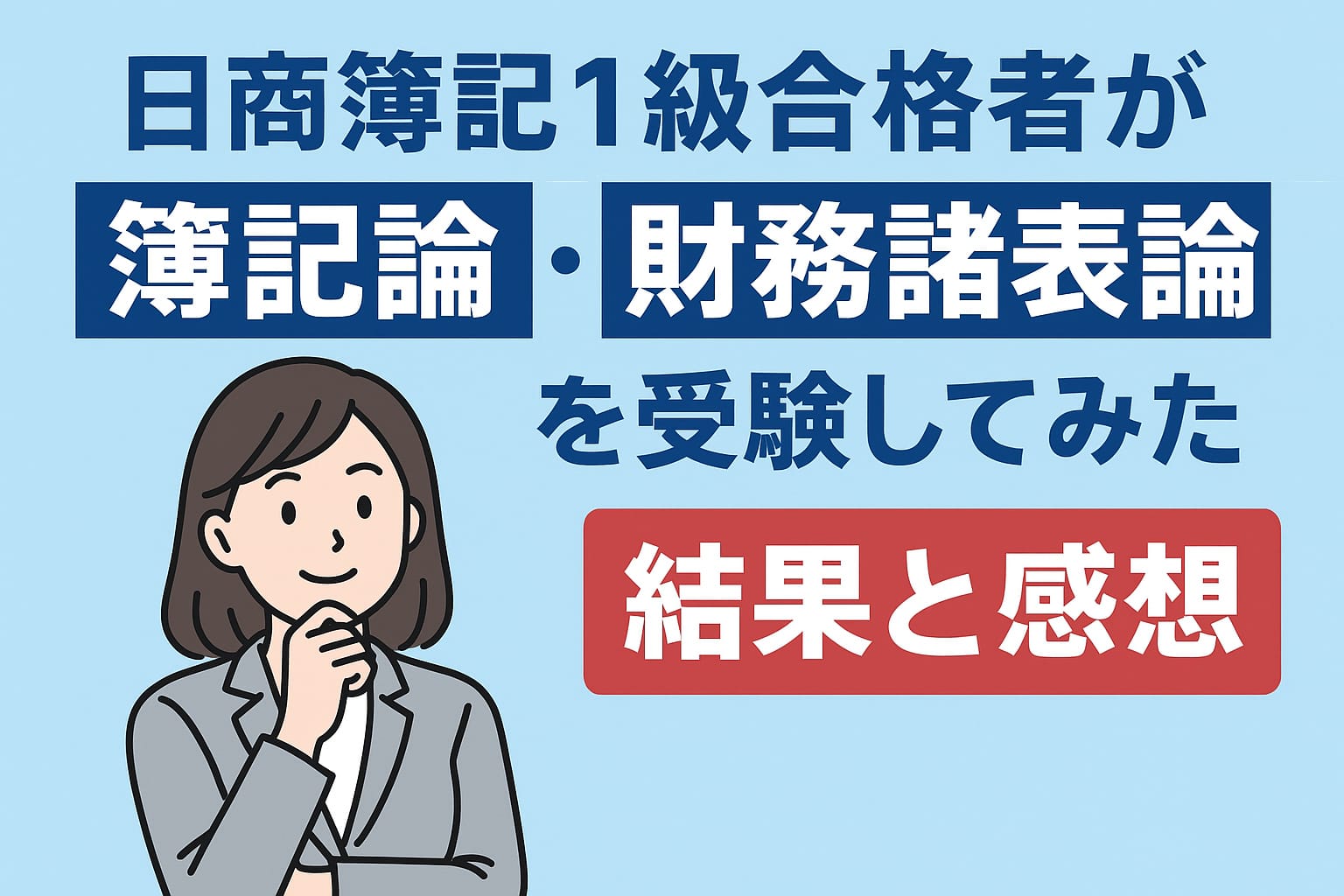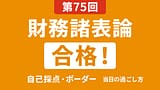筆者のスタートのレベル
- 日商簿記2級、1級合格
- 公認会計士試験の短答式試験を複数回受験したが、合格できず挫折
きっかけ
- 日商簿記1級と簿記論・財務諸表論は同等レベルの難易度と言われている
- 試験範囲が丸被り
- 簿記1級持っていると、税法の受験資格になる
- 受験料が安い(2教科で5000円)
どれだけ通用するか、試しに1回だけ受けてみようとなりました。
2024年の9月 勉強開始~4月まで
色々ネットで勉強法を調べた結果、TACの市販の問題集を使って、アウトプット中心に学習しました。
以下、この時期に使った教材です。
- 簿記論 個別計算問題集
- 簿記論 総合計算問題集 基礎編・応用編
- みんなが欲しかった。簿記論 総合問題の解き方・個別問題の解き方
- 財務諸表論 個別計算問題集
- みんなほしかった税理士の教科書&問題集 財務諸表論
- 財務諸表論 理論問題集 基礎編
- みんなが欲しかった。税理士 財務諸表論 計算問題の解き方・理論答案の解き方
解き方の参考書がめちゃくちゃ効果ありました。問題を解いて、解説に講師の講評がある参考書です。
講師が解き方や感想、解かなくていい場所などの解説をしていて、レベル感を掴むのに最適でした。
解いて間違えた問題を、ankiというアプリに入れて毎日復習しました。
簿記論・財務諸表論のインプットに時間がかからない分余力があったので、10月から上記と並行して、大原の国税徴収法の講義を受講していました。
2025年5月から直前対策
5月に入り、簿記論・財務諸表論は大原の直前対策パックを受講。
毎週答練(2時間×2教科)を解く必要があり、結構大変でした。
間違えた部分を直して、ankiに取り込み、それを復習。
5月から7月まで、このサイクルをずっと毎週やる必要がありました。
解答を見れば理解できたので、解説講義はほぼ見てないです。試しに少しだけ見ましたが、必要ないと思いました。
はじめのうちは、答練の形式に慣れずに、得点率下位70%程度でした。かなり絶望的で焦りました。
特に財務諸表論がひどかった。
理論問題が全然わからないし、計算も総合問題の回答欄の多さや勘定科目まで書かされるため時間が足りません。しかも財務諸表論特有の勘定科目なので、初見の勘定科目をたくさん見て、まずいと思いました。
「簿記論より財務諸表論のほうが計算が簡単だから対策あまり要らない」とネットで見ていたのでショックが大きかったです。「財務諸表論のほうが難しくね!?」となりました。
忙しくて国税徴収法は手が回らなくなったので、6月からは簿記論、財務諸表論に絞りました。
答練を解く→直す→復習するのサイクルの結果、答練に慣れていって、かなり点は取れるようになりました。
基本的に簿記論のほうが成績が良かったです。上位3割程度の得点力でした。
直前期の理論
答練に加え、財務諸表論の理論の暗記をしていました。
10月ごろからTACの市販の教科書や問題集でわからないものを、片っ端からankiにいれて覚えていましたが、中々覚えられず焦りました。
今までの試験の理論対策では理解していたり、キーワードが書ければよかったのですが、文になると覚え方や難易度が違います。
大原の要点チェックノートという教材を合格者で使っている人が多いので、6月後半から使い始めました。
ひたすら毎日、解答を隠して暗唱できるかテストしました。
★★、★、★なしの3段階の重要度別になっているので、★★だけを1周。★だけを1周。などしてメリハリをつけつつ毎日周回していた。
試験本番
試験当日、まじで暑かったです。日中の気温が37度とか。ホームがサウナ状態。
受験者の年齢層は結構高めでした。会計士試験は若い人が圧倒的に多かったです。働きながら受けやすいのが税理士試験のいいところですね。
水500ml1本じゃ足りないので注意。でも飲みすぎても試験中トイレ行きたくなるので注意。
試験開始から30分はトイレいけないです。財務諸表論トイレいきた過ぎて、頭真っ白で総合問題解いてました。
結果
結果は簿記論50点弱。(大原ボーダー55点)財務諸表論73点程度(大原ボーダー68点)。
簿記論は総合問題が初見の形式で出て焦りましたが、33点ほど取れました。
しかし個別問題のほうが、壊滅的でした。精算表の問題が初見でわからず、ストックオプションなどももたつき、時間が足りず、圧倒的に基礎力不足を感じました。
財務諸表論は総合問題がめちゃくちゃ簡単でした。理論も難易度低かったです。
大原の要点チェックノートでやったとこがまんま出てくる問題でした。直前に要点チェックノートやってなければ、ボーダー超えられなかったです。
試験を受ける前は、答練の成績的から鑑みて、「簿記論が本命で、財務諸表論は理論対策足りてないから落ちるだろう」と予想していましたが、結果は逆になりました。
本番は何が起こるかわかりませんね。
日商簿記1級と簿記論・財務諸表論の難易度の比較
受けた感想としては、簿記論と財務諸表論は日商簿記1級と同等の難易度だと思います。
母集団のレベルは、簿記論・財務諸表論のほうが少し高いような気がします。
1級は管理会計論が大変な理由の一つですが、簿記論は個別問題の深さや時間制限のシビアさ、財務諸表論は理論の記述対策や総合問題の回答欄の多さなど、別アングルの難しさがあります。
1級を持っているからと言って当たり前に合格できるわけではなく、やるべきことをこなして、試験に適した状態に持っていく必要があります。
また、税理士試験は年に1回しか受験できない事や、試験発表まで4か月もあることなど、苦しい点もあります。
さらに税理士試験の中では、簿記論と財務諸表論は難易度が低いほうで、本当に大変なのは税法ということです。さすが難関資格だなと思いました。
課題、次に向けて
簿記論は、他の受験生が得点できている個別問題が解けていないので、基礎力が不足していると感じました。
市販の問題集+直前対策パックだけじゃ足りなかったですね。
なので次は基礎力を強化するために、今は大原で初学者コースからやり直しています。
はじめは経験者コースを選んだのですが、基本的に基礎を飛ばして、応用の宿題などが出されるので「これでは穴が埋まらない」と思い、初学者講義に変更しました。
実際初学者コースに変えてみて、既にメリットを感じています。
基礎からしっかり説明してくれるので、自分の穴を埋めやすく、わかるところはどんどん飛ばせるので、負担も少ないです。
宿題も超基礎的な問題が出題されるのですが、そのレベルの問題ですら間違えることがあります。そこに明確に自分の弱点があるので、これらを1つずつ改善していきます。
11月末に結果発表なので、財務諸表論の合否がまだわからないのですが、合格できていれば来年は簿記論と国税徴収法を受験します。
税理士試験は合格発表まで4か月弱あるのが、メンタル的にしんどい点の1つですね。
ボーダーを超えていても落ちることも普通にあるようなので、終わったことは考えず、とにかく今できることに専念するしかありません。